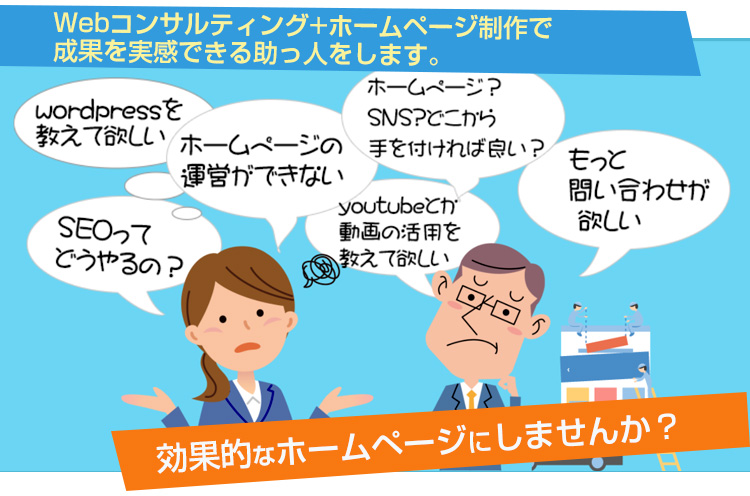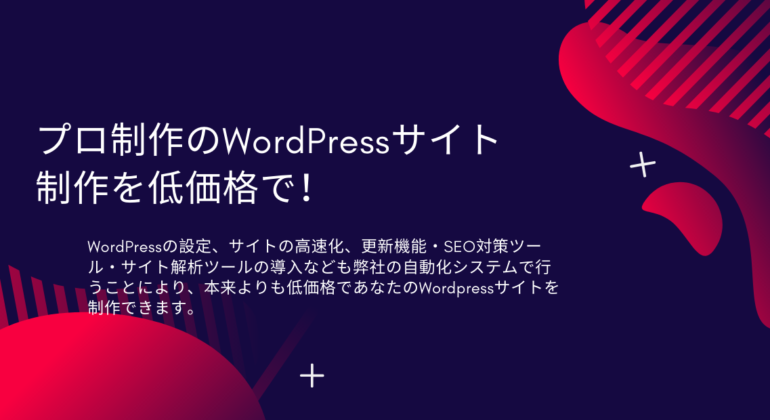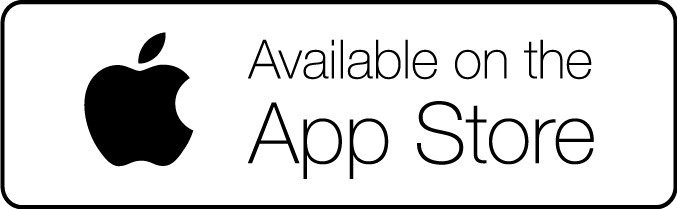AI時代におけるホームページとSNSの連動の重要性:ビジネス成功のためにホームページが必要な理由とは?
AI時代におけるホームページとSNSの連動の重要性:ビジネス成功のためにホームページが必要な理由とは? SNSとLINEだけでの集客はもう限界?AI時代にホームページ制作が再び注目される理由とその未来を解説 1. ホームページの役割の変遷:過去と現在 かつて、企業や個人事業主がビジネスを行う際、ホームページはオンラインプレゼンスを確立するために不可欠なものでした。顧客がサービスや商品について調べるための主要な情報源として、ホームページが機能していたのです。しかし、近年、SNSやLINEの普及によって、多くのビジネスオーナーが**「SNSだけで十分」**と考えるようになりました。 特に、フリーランスや個人事業主、ユーチューバーやインスタグラマーなどが、SNSの手軽さや即時性に依存し、ホームページ制作の必要性を軽視する傾向が強まっています。これにより、ホームページを持たない企業や個人が増え、結果としてホームページ制作に予算をかけないケースが目立つようになりました。 2. なぜSNSだけでは不十分なのか?SNSの限界と課題 SNSは確かに、情報発信や顧客とのコミュニケーションにおいて非常に効果的です。しかし、SNSには次のような限界があります。 2-1. 情報の一過性 SNSの投稿は、時間が経つとフィードの中に埋もれてしまい、顧客が過去の情報を探すことが難しくなります。特にInstagramやTwitterのようなプラットフォームでは、投稿の寿命が非常に短いため、持続的な情報提供には向いていません。 2-2. プラットフォーム依存のリスク SNSプラットフォームは外部の企業によって管理されているため、アルゴリズムの変更やアカウントの削除など、ビジネスに不利な影響を受けるリスクがあります。これに対し、ホームページは自社で管理できる独立した資産であり、外部要因に左右されにくいのが大きなメリットです。 2-3. 検索エンジンでの露出が難しい SNSのコンテンツは、Googleなどの検索エンジンで表示されることが少なく、検索流入が見込めません。一方、ホームページはSEO対策を行うことで、検索エンジンからのアクセスを獲得することができます。これは、SNSにはない強みです。 3. AIとSNSが進化する未来:ホームページとの連携が必要な理由 近年、AI技術の発展により、SNSやホー […] …
画像はリサイズして使いましょう! 〜重いサイトにしないために
画像はリサイズして使いましょう! 〜重いサイトにしないために WEBサイトをお持ちの会社様は、ご自身でブログやイベントページの更新を行っている場合も多いですよね。 その更新の際に、「画像は大きほど画質がいいよね?なら画質が良い方がいい!」と、むやみに大きい画像をアップしてしまっていませんか? 確かに、画質が悪い写真よりも綺麗な写真の方が魅力的。 でも、もしかしたら不要な大きさかもしれません。 大きすぎるサイズの画像のアップを続けていると、サイトがどんどん重くなってしまうため、画像はリサイズして掲載しましょう! では、適切な大きさの画像にリサイズするにはどうすればいいのか。 Photoshopなどの画像編集ソフトを持っていない方でもできる方法を教えます! ぜひご活用ください。 適切な画像サイズを調べようまずは、どの大きさに合わせたら良いのかを調べましょう。 WEBサイトの一番大きく画像が載るページで調査してみてくださいね。 (ブログなど大抵の場合は、詳細ページが一番大きく表示されます。) ※画像をクリックして拡大表示して見れるようにしたい場合は注意が必要です。 この機能を使う場合はリサイズしてしまうとそれよりも大きい画像で表示されません。 クリックしても大きくならない、意味のない機能になってしまいます。 この場合はクリックした後の大きさ(拡大時の大きさ)を基準にリサイズしてください。 それでは例として、弊社ブログでの画像サイズを調べてみましょう。 【Google Chromeをお使いの場合】 1.画像の上で右クリックし、「検証」をクリックします。 2.ソースコードが表示されます。 その左上部分に、矢印のマークがあるので、クリックします。 3.その状態で、画像にカーソルを合わせると、細かな情報が表示されます。 その中でも、右上に表示されているのが画像サイズです。 今回は 横が750.19 縦が514.5 ということですね!(なんだか半端な数字ですが…) ※注意点 レスポンシブサイトは、見ているウィンドウの大きさで画像の表示サイズが変わります。 小さいウィンドウで確認している場合は、画像も小さく表示されるため、画像の表示サイズを正確に調べる時には、フルスクリーンで確認してください。 【Internet Explorerをお使いの場合】 1.画像の上で右クリックし、プロパ […] …
企業にとってのホームページの役割と運用目的を再確認
企業にとってのホームページの役割と運用目的を再確認 「ホームページは持っているけど、立ち上げてからほとんど触っていない」 「作ったはいいけど、どう運用していけばいいかわからない」 「忙しくて更新している暇がない」 など、自社のホームページはあるけれど、上手く活用できていない企業は多いようです。 SNSやアプリなどを使ったデジタルマーケティングが盛んになってきた近年、そちらの更新は頻繁に行っているけれど、ホームページの更新がおざなりになってしまったり、数年前に更新した状態で放置されていたりといった例は、まだまだ多いように見受けられます。 そこで今回は、自社のホームページの役割と運営目的についてお話ししたいと思います。 今後、デジタルシフトの流れはさらに加速していきますので、放置していたホームページを再確認してみましょう! Webマーケティングにおけるホームページの役割とはスマートフォンやタブレットが普及し、誰でも簡単に、且つ手軽に情報収集ができるようになってから、消費者が企業により多くの情報を求めるようになりました。 例えば、単なる商品情報だけでなく、 ・素材や原材料がどこのモノであるか ・本当に安全なものか ・その買い物で得る価値は何なのか など、消費者が購入に至るまでに知りたい情報は以前よりも多くなっているのです。 その背景には、情報が手に入りやすくなったことで、モノの比較検討が容易にできるようになったことや、他の消費者の意見が見えるようになったこと、商品やサービスに対する専門知識が消費者でも得られるようになり、より高いサービス・商品価値を求めるようになったことが挙げられるのではないかと思います。 ですから、ホームページの役割を「商品やサービスの特徴や魅力を消費者のニーズに応えて伝えること」とするならば、その時代の消費者のニーズに合わせてホームページは変えていく必要があります。 企業の都合で情報提供を行うという考えではなく、消費者のニーズに応じた情報をホームページで発信していくということが、本来のホームページにおける役割ではないでしょうか。 自社サイトはきちんと更新されていますか?自社のホームページは、更新されていますか? また、どのようなページがあり、どんな情報を発信しているか把握していますか? 企業の規模が大きくなると、各部門や部署で別々にホームページを管理 […] …
「デザインお願いします」と言われてデザイナーは何を考えてデザインしているの?
「デザインお願いします」と言われてデザイナーは何を考えてデザインしているの? まずは「絶対に譲れないもの」を明確にする たとえば、お話を進めていくとこんな要望があがってきます。 会社のロゴがこういうデザインなので、メインの色はこの色がいいなあ製品を写真で大きく見せたいのでインパクトがほしいなあSEOに力を入れていきたいので、キーワードをたくさん入れられるようにしてほしいWEBサイトにはこんな動きをつけられたらかっこいいな!ユーザーは年配の人が多いので、文字は小さくしたくない など。 この時点でお客様にとって「絶対に譲れないもの」をしっかり理解しておきます。 どんなにかっこいいデザインにしても、狙ったユーザーのためになっていなければ意味がないのでお客様の要望と、こちらからのアドバイスをうまくまとめていきます。 「こんな雰囲気はどうだろう?」参考になるデザインを社内で共有して意見を出し合う 参考デザインは、ゴールに向けて「私たちが向かっているゴールとは何か」を関わる人みんなで共有するためのものです。 基本的にはデザイナーが参考デザインを探しますが、構成を考えたディレクターの頭の中にも少なからず完成形のイメージがあるはずです。 それがバラバラのまま進めるとうまくいかないので、ここで共有してゴールを明確にしていきます。 いざデザイン! ゴールが決まったので、デザインをしていきます。 私の場合は真っ白なキャンバスを眺めていても時が勝手に流れてしまうだけなので、とにかく思いついたものを配置していきます。(手書きでラフを描いていく人もいます) ・メインカラーはこれにしよう ・メインカラーに合わせてアクセントカラーはこんな色がいいかな ・このキャッチコピーにはこういうフォントが合いそう ・英語や数字はかっこいいイメージに合うものを選ぼう こんなことを考えながら手を動かしていきます。(この間は結構自由な思考回路で私は「デザインを楽しむ」ことに没頭します) そして、途中途中で客観的に見る時間を設けます。 「この色で本当に大丈夫かな」 「この文字サイズで、これくらい行と行の間が広いと読みにくいのでは…?」 「写真がこんなに大きいとノートパソコンだとかえって見にくいのでは」 と、ここであえて自分の作ったものにケチをつけてみます。 ここからが頭を使ってたくさん考えるモードです! 行き詰まっ […] …
在宅でできるWebデザインを副業にしよう♪初心者におすすめの仕事は?
在宅でできるWebデザインを副業にしよう♪初心者におすすめの仕事は? 政府は働き方改革を実現するため、長時間労働の是正、仕事と子育てや介護の両立の他、テレワークや副業などの柔軟な働き方についても推進する活動を行っています。副業に関するニュースを耳にする機会も増え、副業に興味をお持ちの方も多いでしょう。今回は副業におすすめしたいWebデザイン系の仕事と必要なスキルについてご紹介します副業を始める人は増えている!これまで、公務の遂行上問題があるとして、公務員の副業は禁止されていました。しかし2020年1月、総務省は各自治体に対し、公務員が報酬のある活動に参加する許可を得るための分かりやすい許可基準を作るように求める通知を出し、公務員の副業が解禁される時代がやってくるとして、大変話題になりました。 一般企業であっても、社員の能力向上や視野拡大などを目的に、副業を解禁する企業も増えています。それに伴い、派遣社員の方も副業が認められるケースが増えたため、スキルアップを目的として副業を開始する方も増えています。 副業の市場規模2018年1月、厚生労働省は「働き方改革実行計画」をふまえて「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しました。その結果、2018年は「副業元年」と呼ばれて副業が大いに注目されることとなりました。また、不特定多数の人に業務委託を行う「クラウドソーシングサービス」が登場したことも、副業が拡大する大きなきっかけとなりました。 そのクラウドソーシングサービスを提供するランサーズ株式会社が発表した『フリーランス実態調査2018年度版』によると、副業フリーランスの経済規模は前年から1.5兆円増え、8兆円近いそうです。 広義のフリーランスのうち、副業(本業・副業を区別しない労働者を含む)フリーランスの数は744万人、経済規模は7兆8280億円となり8兆円近い規模になりました。ランサーズ「フリーランス実態調査 2018年版を発表」より Webデザインを副業におすすめする理由Webデザインを副業におすすめする理由本業と掛け持ちで仕事をする場合、限られた時間を効率良く使うことが重要です。在宅でできる仕事が多いWeb業界は、副業に適しています。クライアントとの打ち合わせをテレビ電話やチャット、メール等で済ませることができる案件などもあり、パソコンが1台あれば仕事をするこ […] …
ITで働き方改革!クラウド、テレワークの新しい仕事の形とは
ITで働き方改革!クラウド、テレワークの新しい仕事の形とは 従来は毎朝同じ時間にオフィスに出社して働くことが当たり前でしたが、最近は仕事に対する意識も変化し、働き方が多様化しています。政府は多様な働き方を推進しており、企業はその実現のためにクラウドやテレワークなどのIT技術の導入を進めています。今回は働き方改革におけるIT活用、これからの働き方にマッチするWeb業界、そして働き方改革のIT活用を支えるIT技術者の需要増についてご紹介します。 働き方改革とは近年、「働き方改革」という言葉が新聞やニュースで取り上げられていますが、果たしてどのような政策なのでしょうか。 働き方改革は端的に言うと、日本の企業や職場における働き方に対する考え方や雇用形態、制約を一新し、新しい働き方を模索する改革です。日本の労働人口は2008年をピークに減少しているため、労働力不足を解消するために「長時間労働の是正」「正規雇用と非正規雇用間の格差是正」「女性や高齢者、障害がある方が就労しやすい環境への整備」「企業における副業の容認」など、一人一人に合った働き方の実現を目指しています。 すでに、働き方改革実現進会議が提出した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」は2018年6月29日に可決・成立し、2019年4月から施行されています。 働き方改革は、日本が抱える社会問題の解決と同時に、働く人のQOL(生活の質)を高める効果としても期待をされています。 働き方改革とIT長時間労働は健康に悪影響を及ぼすだけでなく、仕事と生活との両立を困難にし、少子化や女性のキャリア形成阻害の一因となります。そのため最近は仕事と生活を調和させる「ワークライフバランス」という考え方が広く受け入れられるようになっています。 つまり、忙しいことが美徳とされ、長時間の残業や有給休暇の未消化が当たり前の時代から、限られた時間を有効活用していかに成果を出すかという時代にシフトしているのです。この働き方を改革する手段の1つとしてテレワークが期待されています。 テレワークと就業場所による分類テレワークと就業場所による分類「テレワーク(telework)」とは、離れた場所を表す「tele」と働くことを表す「work」を合わせた造語です。テレワークは働く場所によって、在宅勤務、モバイルワーク、サテ […] …
働きながらWebプログラミングスクールに通う方法
働きながらWebプログラミングスクールに通う方法 スキルアップのため、Webプログラミングを学ぶ方が増えています。社会人が働きながらITやWebの知識・技術を学ぶ場合、独学よりも専門の講師がいるWebスクールで勉強した方が、短期間でWebのトレンドや現場で必要とされる技術を学べるため効率的です。 それでは、どのようなポイントに注意してスクールを選べば良いのでしょうか。今回は社会人がWebプログラミングスクールに通う方法と、良いスクールの選び方についてご紹介します。【1】予約を取りやすいスクールを選ぶ【1】予約を取りやすいスクールを選ぶ社会人の方がプログラミングの勉強をするためにWebが学べるスクールに通う場合、仕事帰りや休日に予約を入れるケースが多いでしょう。職種によっては「急な仕事が入った」「予定よりも早く仕事が終わった」など、スケジュールの変更も少なくありません。 そのため、フリータイム制など、空き時間にすぐに授業の予約を入れられる予約システムのプログラミングスクールを選ぶことをおすすめします。自分の都合に合わせて自由に授業の曜日や時間を変更できるフリータイム制度は、勉強時間の工面が厳しい社会人の方にぴったりです。 また、ビデオ学習による予習・復習や、授業以外の時間でも自由に学習ができるラーニングスペースがあるかどうかも、自分のペースで勉強を続けるためにチェックしておきたいポイントです。 Webプログラミングを勉強するなら学校へ!Webスクールに通うメリット やはりプログラミングの独学は難しい?挫折しない勉強法4つのポイント【2】短期集中で学べるスクールを選ぶ【2】短期集中で学べるスクールを選ぶ働きながら学ぶ社会人が長期間にわたって勉強時間を確保することは、容易ではありません。仕事とプログラミングスクールの通学を両立する場合は、短期間で修了するカリキュラムを選び、受講期間中に集中して学習することが大切です。1日の授業時間は、2時間程度でも構いません。 ただし、短期間で講座が終わることばかりに注目してスクールを選ばないよう注意してください。受講期間が短いだけで授業内容が伴わないようでは、何も身に付けることができません。Webプログラミングの勉強は覚えることが多く実践力こそが重要なため、カリキュラムの内容が充実しているかどうかはとても重要なポイントです。プログラミ […] …
フリーランスのWebデザイナーが仕事を効率良くする方法とは?
フリーランスのWebデザイナーが仕事を効率良くする方法とは? フリーランスに憧れ、Webデザインの勉強をして、さあWebデザイナーデビュー! といっても、いきなり仕事の方からきてくれるわけではありません。Webデザインの仕事は数多ありますが、まずはその中から自分のスキルにあった仕事を受注する必要があります。 効率よく仕事をゲットするためには、どうするのがいいでしょうか?今回は、フリーランスとして仕事を始めたばかりのWebデザイナーが、仕事をGETするためのノウハウをご紹介します。ポートフォリオを作るポートフォリオとは、Webデザイナーが自分自身の実績や能力、人柄をアピールするための作品集です。(異なる業界では別の意味で使われることもあります。) 就職活動時にも必要なものですが、フリーランスにとっては、仕事を受注するための重要な営業ツールでもあります。自分のスキルを適切に示すことができる様々なテイストの作品を多数掲載しておきましょう。 自分にできる最高の技術で、丁寧に作りこむポートフォリオは、フリーランスクリエイターの技術やセンスを証明するための大切な自己PR方法です。 ポートフォリオ自体が作品ですので、丁寧に作りこみます。 質の良いポートフォリオを作るためには、優れたクリエイターのポートフォリオを多数閲覧して参考にするのがいいでしょう。インターネット上にも、ポートフォリオを紹介したまとめサイトがあります。 掲載する作品がない場合は?自分の好きなもの、趣味、前職の業界などをテーマに、オリジナル作品を作って掲載しましょう。また、写真サイトやイラストなど、好きなものや得意分野について掲載しておくことは、仕事をとる際にも有益です。 このクリエイターがどんな分野に興味や関心を持っているのかが発注者にもわかるので、好きなものや趣味に関連した仕事がくる可能性があります。 ポートフォリオ掲載許可を事前に取っておくある程度までポートフォリオが完成したら、仕事を受けつつ掲載作品数を増やしていきたいものです。 仕事を受ける際にあらかじめ、ポートフォリオへの掲載許可をとっておきましょう。 フリーランスのための案件紹介サイトやクラウドソーシングサービスを利用するフリーランスを始めたての方ならば、このやり方で仕事をもらっている人は多いでしょう。 ただし、クラウドソーシングサービスに関しては、 […] …
プログラマーとは?プログラマーの種類と将来性
プログラマーとは?プログラマーの種類と将来性 最近、「プログラマー」というワードをよく耳にしますが、どのような職業なのかご存知でしょうか?プログラマーとは、プログラミング言語を用いてシステム開発を行う職種のことです。システムエンジニア(SE)と混同しがちですが、厳密にいうと、システム開発全体の指示や開発したシステムがうまく動作するかテストを行うのがシステムエンジニアで、システムエンジニアが設計した仕様書通りにシステムが作動するようプログラムを書き上げるのがプログラマーです。 さまざまな種類のプログラマーが存在するため、その種類によって仕事内容や使用するプログラミング言語は異なってきます。発展の著しい昨今のIT業界では、プログラマーに対する需要が増加してきています。注目の職種ですね。今回は、主なプログラマーの種類と将来性、プログラマーになるために必要なことをご紹介していきます。プログラマーに興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください!プログラマーにはどんな種類がある?プログラマーと一口に言っても、さまざまな種類のプログラマーが存在します。明確に分類することは難しいのですが、ここでは大まかに5種類のプログラマーの例を挙げていきます。 Webプログラマーprogrammer-kind-futureWebプログラマーの業務は、Webサイトに特化したプログラミングが中心であり、Webシステムの開発を行います。インターネットショッピングを例に挙げると、「買いたい商品を検索」→「検索結果の商品を表示」→「商品がクリックされると詳細ページへ移動」このような一連の流れは、すべてWebプログラマーが書き上げたプログラムによって実行されます。また、多くの人が利用するSNSも、Webプログラマーが構築したプログラミング上で実行されます。 Webプログラマーが使用する主なプログラミング言語としては、「Java」「PHP」「Python」などがあり、さらに記述したプログラムを実際に動かすためのマシンであるサーバーを構築するために「Linux」「Apache」「MySQL」などの技術を学ぶ必要も出てきます。 関連記事 Webプログラマーとは?Webプログラマーの仕事内容と年収 プログラミングを学び始める前の必須知識アプリケーションプログラマー(アプリ開発者)programmer-kind-fu […] …
ネットワークエンジニアとは?ネットワークエンジニアの仕事内容と将来性
ネットワークエンジニアとは?ネットワークエンジニアの仕事内容と将来性 ネットワークエンジニアとは、コンピューターネットワークのシステム構築や保守管理などを行う技術者を指します。ネットワークエンジニアと一口に言っても、仕事内容はさまざまです。今回は、これからネットワークエンジニアを目指す方に向け、ネットワークエンジニアの多岐にわたる仕事内容や将来性についてご紹介します。ネットワークエンジニアの仕事内容ネットワークエンジニアに必要な能力とは?ネットワークエンジニアの仕事内容は、主にネットワーク設計、ネットワーク構築、ネットワーク監視・運用の3つに大別できます。なお、案件やネットワークの規模によっては設計から構築、運用までを一貫して1人の人員が担当することも珍しくありません。 1.ネットワーク設計ネットワークシステムの詳細設計を行う仕事では、セキュリティや各種OS、サーバーなどに関する幅広い知識が求められます。お客様の依頼を受けてネットワークを設計する際は、設計・提案能力はもちろんのこと、ヒアリング力やプロジェクト推進能力なども必要です。 2.ネットワーク構築ネットワークエンジニアは、設計書をもとに回線の設置などネットワーク構築も行います。無駄なコストやトラブルの発生を避けるためには、最新の製品や技術の動向、ケーブリングや機器の設置に関する知識が必須です。 3.ネットワーク監視・運用ネットワーク監視・運用では、ネットワークシステム構築後の維持管理を行います。一度ネットワークを構築してしまえば、障害が起きない限り、ネットワークエンジニアは特別忙しくなることはないため、ネットワーク利用者のトラブル対応、いわゆるコールセンター的な仕事を兼任することもあります。ただし、障害が起きた際の対応にはネットワーク全体を見渡す視野や幅広い知識が必要とされるため、決して難易度の低い業務ではありません。 全授業、通学・オンラインを選べるプログラミングスクール 日本初Web専門スクールのインターネット・アカデミーは、他のスクールとは全く違います。講師、環境、カリキュラム、システム、サポートなど、すべてがWebに特化しているので、初心者を最短距離で最前線へ導くことができるのです。 ネットワークエンジニアに必要な能力とは?ネットワークエンジニアに必要な能力とは?ネットワークエンジニアは、基本的に他 […] …